
退塾率を大幅改善した、チューター教育とは?ALCSのスタプラ活用術(後編)Customer Story #7|学習塾ALCS
※この記事は、「2種類のコミュニケーションポイントで通塾率をUP。ALCSのスタプラ活用術(前編)Customer Story #6」の続編です。
「みんなが前向きに成長できる場所」。そんなスローガンのもと、生徒の「自己実現力」を育成する学習塾ALCS。Studyplus for Schoolの立ち上げ期から、独自の学習管理方法と組み合わせてご活用いただいております。
前編・後編に渡り、生徒とのコミュニケーションをどのように設計しているのか、Studyplus for Schoolをどのように使っているのか、ALCS代表 小川武志氏にお話を伺いました。
他のチューターのカルテを見ることで成長を促す

ー2018年に実装されたスタッフボードはどのようにご利用いただいていますか?
校舎運営のプラットフォームとして、重要事項の全体共有や、日報の提出をしています。「この子たち入ったからよろしくね」「このPOPを書いておいて」「今こんなことをしています」など、チューターとのコミュニケーションの場所にしています。
ーチューターとのコミュニケーションで、面談の方法や学習管理のポイントの共有はどのようにしていますか?
私がベースを作成したマニュアルを使っています。去年までチューター研修やってた内容をベースに、別のスタッフにブラッシュアップしてもらっています。


求めることは難しいことではありません。スタッフにも前向きに成長してほしいので、「これだけはおさえよう」という項目を共有し、あとは自分で考えてもらっています。
ーこれだけはおさえてほしいポイントとは?
「頑張ったことを生徒から聞く」「やったことを認めてあげる」「次の一週間やることを宣言させる」などはお願いしています。チュータリングの流れは、ヒアリングして承認して、「じゃあ来週こんなことを頑張ろう」と決めてもらいます。別の人でもチュータリングができるように、カルテはしっかりと書きこむルールです。
ー生徒への接し方の指導はしますか?
タミさんというスタッフのやり方を真似してもらっています。彼女はどんどん話しかけて生徒と仲良くなるのが上手です。入塾した生徒は最初の1か月間、必ずタミさんとチュータリングをします。そのあと他の担当に振っていくという流れにして、タミさんのコミュニケーションをチューターたちに引き継いでもらっています。
あとチューターには「他のチューターのカルテを見てね」と指導しています。紙だとなかなか共有できませんが、デジタルであれば簡単に開けるので、先輩チューターがやっているのを見て学べます。
入退室システムの併用で記録入力率も向上

ー2018年は、入退室システムもStudyplus for Schoolに変更されました。なにか変化はありました?
もともと使っていたシステムは1日分のデータしか残らないもので、「今日、誰がいつ来て、いつ帰った」ということしかわかりませんでした。一人の生徒に関してのレポートが翌月に出てはいたのですが、月ごとの比較もできません。
Studyplus for Schoolなら、いつでもいる時間帯を見れます。全生徒の滞在時間がまとまっており、混み合う時間帯もわかるのでとても便利になりました。
ー記録の習慣では何か変わったことはありましたか?
生徒の記録入力率は上がっています。入退室管理をStudyplus for Schoolにしたことで、通塾時に必ずStudyplusのアプリに触れてもらえるようになりました。
また、チュータリングの時にも「先生はタイムラインを見てるから、必ず記録をつけてね」と記録を促す言葉をかけています。勉強をどれだけしたか、バランスがいいかというのも大切ですが、「日々の勉強をちゃんと塾の先生も見てくれている」と生徒が感じられることが、モチベーションを維持するうえで重要です。
さらに、イベントを開催してモチベーションを刺激しています。季節講習の時期に学習時間ランキングを張り出し、上位の生徒には景品を出しています。
ー盛り上がりますか?
競争原理か、高校3年生を中心に盛り上がります。生徒の横のつながりを生み出すことも心がけています。顔を知らないよりも知っている方が盛り上がるので、チューターが積極的に繋いでいるのです。生徒たちは、学年を超えて交流しています。
また、Studyplus内に、ALCSの生徒を集めた非公開グループを作っています。タイムライン見れば他の生徒の頑張りが流れてくるので刺激になります。
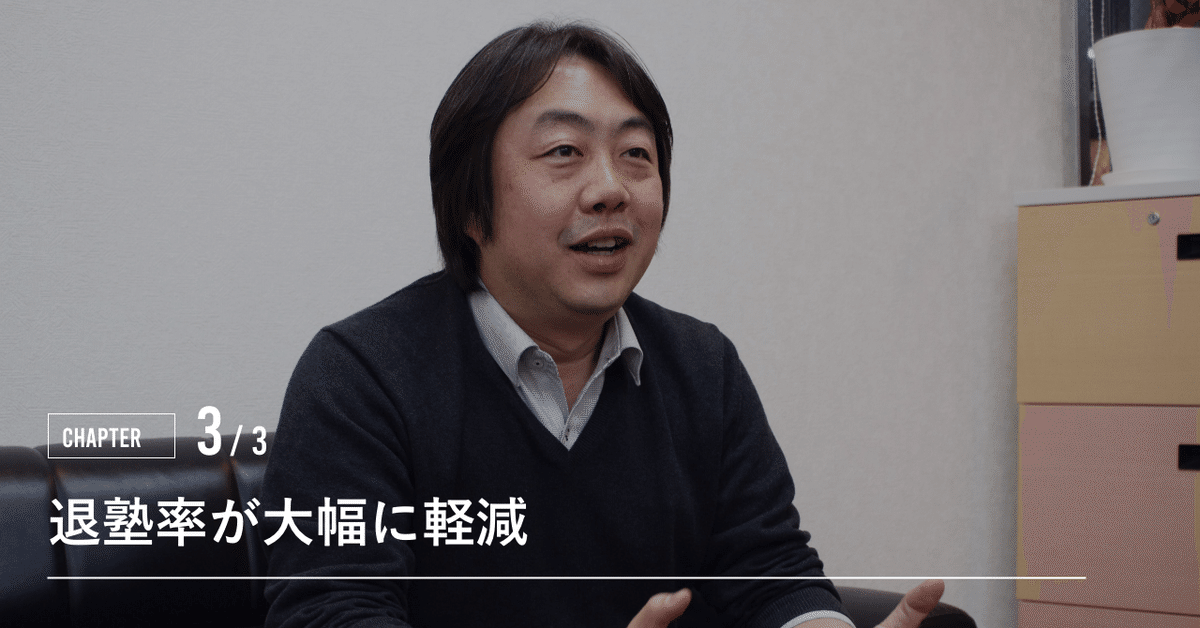
ー映像授業と学習管理ツールの併用についていかがですか?
視聴履歴をすべて、Studyplusに記録してもらっています。毎週カルテで確認できるので、進捗管理がはかどっています。未視聴の映像がたまっている生徒がいたら、チュータリングのなかで「来週までにここをやろう!」と約束します。未視聴がたまると辞めてしまうので、管理してあげることが大事です。
Studyplusで日々の視聴状況を把握しつつ、カルテでも確認するという二重チェックが効果に繋がっていると思います。
ーその他、生徒との関わりにはどんな変化がありましたか?
オフィシャルに生徒と接点を持てることは大きいです。小中学生の時は自宅に頻繁に電話することで接点を強めていたのですが、高校生では部活でそもそも自宅にいないことや、保護者も把握していないことが多く、接点を持ちづらい状況がありました。
Studyplus for School挿入後は、退塾者数がかなり減りました。年間で3割、4割は辞めてしまっていたのが、1人いるかどうかくらいです。
それは生徒をほったらかしにせず、見てあげる、承認してあげるということができているおかげです。複合的な要素はあるにせよ、プラットフォームとして使っているStudyplus for Schoolが核になっているのは間違いないかなと思います。
ー複合的な要素というのは?
チュータリングや受付などの仕組みの改善などです。映像コンテンツは昔から同じものを使っているので、人の動き方の精度が上がったのが要因として考えられます。
情報共有がすごくスムーズにできるようになったので、それによって生徒の孤独感が減り、よく連携できるようになりました。チューター同士も、先輩や仲間の取り組みが見られ、逆にいうと人から見られてしまうので、チューターの意識に良い影響を与えました。
ー最後に、今後実現していきたいことや展望があれば教えてください
塾業界は人手不足で、少ない社員でいかに上手く運営していくかがとても重要な課題です。先生を大量に抱えることが難しい中、Studyplus for Schoolを軸として学生スタッフ中心に回っていくモデルが出来上がれば、田舎や離島も含めて、様々な場所に高校生の居場所を作ってあげられると思っています。
特に地方では中心地から少しでも離れると塾がなくなってしまいます。Studyplus for Schoolで普段の頑張りを承認してあげて、週に1回、月に1回通塾するだけでいい塾を増やすことができれば、地域間の教育格差も埋められると考えています。
***
Studyplus for Schoolについてのお問い合わせはこちら。

